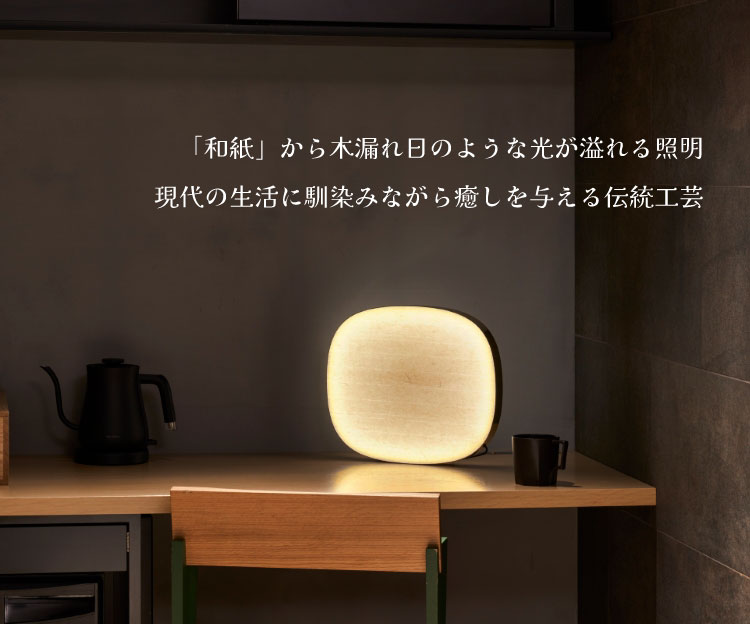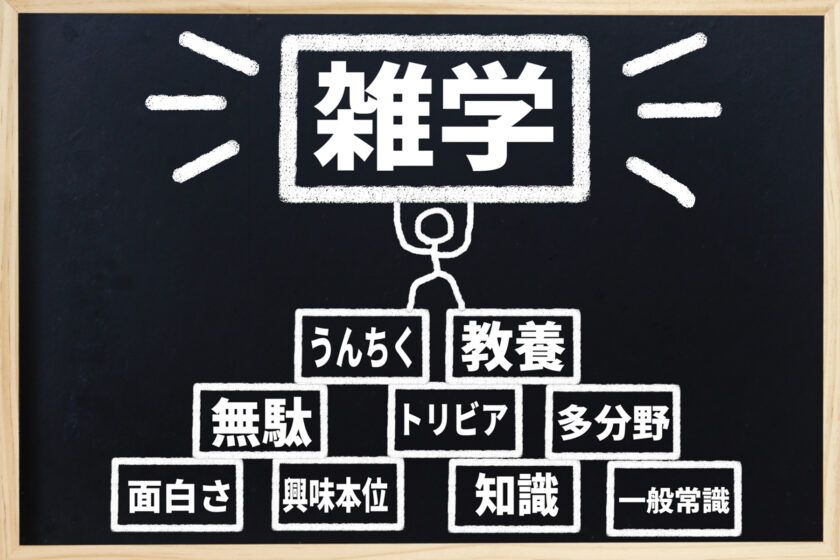橋の向こうに幸せがある――インタビュー中、幾度か出てきた印象的なフレーズです。まるでジョークのようにも聞こえるその言葉は、修業時代に描いた確かな未来予想図でした。
haku硝子(はくがらす)代表の三田村 義弘(みたむら よしひろ)さんは当時、板橋にある自宅から江戸切子の工房に通い、切子職人として研鑽(けんさん)を積み上げていました。修業していた工房から見える景色に常に感じていた切子職人としての姿。
それは年月を重ね、技術が向上するにつれて具体的に、鮮明になっていきます。鳥のひなが巣立ちするかのように、「自分の力で食っていく」ことを常に意識したのもこの時代です。
三田村さんはいったいどんな未来を描いていたのか、それをどうやって実現したのか。お話を伺ってきました。
切子職人としての自立がhaku硝子の創立に

インタビューに伺ったのは8月の晦日。残暑が厳しく、照り付ける日差しが肌には痛いほどです。訪問の約束の時間は10時。工房には8時に入って仕事に向かっている三田村さんの集中力は驚くほどで、私たちの訪問を一瞬ど忘れするほど。それもそのはず、彼の手掛ける切子は文様が緻密(ちみつ)で繊細です。それも大まかにペンであたりを付ける以外は特に削るためのガイドなどありません。時間を忘れて作業に没頭するのは当たり前なのです。
「この世界はとても高給取りとは言えませんよ」。作業の手を止めて静かにお話してくれました。ガレージを改装した工房は江東区森下にあります。三田村さんが夢に描いていた橋向こうの土地。ここは切子の磨き屋さんや取引先に近いロケーションで、かつ今の住まいである木場からは程よく離れています。
工房は切子職人と自立するときにちょうど出会った物件でした。ビルの所有者が1階のガレージを改装し、事務所として使えるようにしつらえていたものです。
たまたま出会った物件とはいいながら、そこは常にビジョンに描いていたエリアに位置するもの。切子職人として修業し始めた当初は職人として独立するという夢の目標は、むしろ修業の厳しさなどから逃れるためのぼんやりとしたものでしたが、技術を修得し職人として働きだすと、仕事をこなせるようになっても給金が上がらないという現実に直面します。
「自立するには切子職人として独立するほかない」と明確に認識したのが入って3~4年たった頃。当時は独立が目下の目標でした。
切子業界が直面している厳しい現実を目の当たりにして

モノが売れないこの時代、江戸切子製造業もまた厳しい現実に直面しています。この業界では熟練した技術が必要であるにも関わらず、それに見合った対価が与えられていない。つまり労働賃金が低く、いわゆる下請け事業、零細産業と形容されていることが常態化しているのです。
これに追い打ちをかけているのが「高齢化」です。賃金が安いことから人材が集まりにくく、それゆえに慢性的な人材不足に陥っているのです。
「ぼんやりとした、しかし確かな不安」自分のやりたいことに向き合う。

大学では経済学を専攻した三田村さん、なぜ江戸切子職人を選んだのでしょうか。
今から18年前ほどのことです。彼もまた3年生から始まる就職活動の前線にいたのですが、企業説明会や学校の行う就職セミナーなどに参加しているうち、自分の中に言い知れぬ違和感を覚えたと言います。
「この仕事を長くやっていけるのだろうか」そのはっきりとしない不安は、就職活動を熱心にこなせばこなすほど強くなっていきます。
もともと人と接することに苦手意識があった彼は、ここにきて人生の舵を大きく切ります。できるだけ個に没入できる仕事がしたい。たどり着いた答えは職人でした。
三田村さんの父親が美術本の出版を手掛けていたことから、美術館や展覧会への招待券を譲り受け、多くの美術品などを見る機会に恵まれます。それが職業模索の素地となったのか、細やかな技術が必要な細工物の職人になりたいと思うようになります。その結果、今の仕事にたどり着きます。
「切子職人では食っていけない!」切迫した思いが腕を磨く。

徒弟として切子職人の世界に飛び込んだ三田村さんでしたが、8年間は実家である板橋から通いで修業を続けざるを得ませんでした。修業を始めた頃はまだしも、百貨店などで受注した仕事をこなすようになっても賃金が上がらず、都内でワンルームを借りるなど現実として考えられない状況でした。
百貨店でモノが売れない昨今にあってはそれを理由に賃金は低いままに据え置かれました。このままでは本当に食っていけない。食っていくにはどうしたらよいのかを考えあぐね、橋の向こうを眺めます。すると「江戸切子職人としての独立」がますます明確に、具体的になっていくのです。
独立するにはどうしたらよいのか。それは製造業に携わる者ならごく当たり前の「良い製品づくり」に励み、商品を多く世に出すことに尽きます。独立を目指すとおのずと高単価の仕事を受注するという好循環が生まれます。技術が磨かれ、効率よく作業できるようになり、工賃の高い商品の製作がめぐってくるように。
さらにバイヤーにその技術を見込まれ、より賃金の高い工房へ紹介してもらったり、独立の後押しとして工芸展への出品の道筋を立ててもらったりと、精進する彼に次々に幸運が舞い込みます。
これまでの経緯を「運がよかった」と謙遜して言う三田村さん。それが単に運の良さだけではないことは彼の手掛けたものを見ればわかります。彼のひたむきな仕事に対する姿勢は、手掛ける商品に如実に表れているからです。
繊細でありながら、ダイナミックな勢いを感じられる細工。手掛けたものは商品であり、作品ではないとする飽くまでも職人目線で物を語るところなど、独立した腕のある職人にありがちな自己顕示欲はありません。

独立後の思い――「自分のような職人を増やしたい」

独立して現工房に移ってから3年ですが、バイヤーから受注した仕事をこなすのに手が足りないほど多忙な毎日を送っています。工房の空きスペースはそのうちギャラリーとして自分の手掛けた商品を展示・即売するスペースとして活用したいという構想もあります。
また、江戸切子の技術を施した帯どめやペンダントヘッドなどの宝飾品にも手を広げたいという思いも。しかしそれに踏み切れないのは「職人気質(しょくにんかたぎ)」、それに尽きます。「自分の技術を高く評価して仕事を卸してくれるバイヤーの期待を裏切るわけにはいかない」と、今は目の前にある仕事をひたすら納期に遅れなくこなすことに注力しているのです。
良い仕事をすれば仕事が増える、仕事が増えれば自分でやりたいことは後回しになってしまう――ワンオペでこなしていくには限界を感じはじめ、オウンドサイトでサイト管理のできる切子職人見習いのような人材を募集し始めました。
「実はどんな人でもこの工房に入りやすいように、屋号に三田村姓を冠していないのです」。haku硝子のhakuの由来は「余白」からきているということはウェブにも記載されていたのですが、だれもがこの業界に入りやすいよう、まっさらの何もない状態である「白(はく)」の意味を掛けているというのです。
「この業界には問題点が多い。それは職人が自立できないこと、実子を後継者にするとき、修業に甘さが出てくること」彼は従来のこの業界にありがちな問題点を打破していくことがこの工房の存続にも関わっていくと考えているようでした。
三田村さんは10年スパンで自分のこれからのあり方を模索しています。
30代までの約10年間は職人として成長の時期、40代までを職人としての熟成期、そしてこれから先の10年は工房の組織力強化のための種まきの時期だと考えているのです。
40歳を目前にして種まきを開始し始めた今、ゆくゆくはhaku硝子で自分のように独立して食える職人を増やしたい、それが自然に工房を大きく成長させることにつながると、三田村さんは考えています。

「モノづくりの基本と常識に忠実でいたい」それが伝統工芸士の肩書にこだわらない理由。
この業界に飛び込んで10余年、伝統工芸士としての資格を取得できるようになったと思いきや、今は仕事に忙しく、その試験も受けられない状況が続いています。
「資格にはこだわらない」それが率直な回答でした。なぜか? ひとつは伝統工芸士という肩書に乗じて技術の研鑽を怠る職人が少なからずいることを指摘します。
この仕事は技術的なものだけでなく、体力的な衰えも如実に商品に現れると言います。それを伝統工芸士というだけで、おぼつかなくなった技術を披露するのは自身の信条に合わないのでしょう。
その一方で、この年になって子供を持つ身となった今、伝統工芸士というタイトルを獲得して自分を支えてくれた両親や妻子を喜ばせたいという思いもあります。
取材を終えて

三田村さんの工房「haku硝子」は、まだ看板がありません。日々の仕事に追われ、それをこなすのに朝8時から夜11時まで作業に没頭する日々が続いています。オウンドサイトは知り合いが作成してくれたと言いますが、切子職人としての矜持から、きちんとビジネスとしてお金をかけ、更新も続けています。
オウンドサイトでの人材募集がうまくいけば、今は殺風景な景色も、色とりどりの輝きを放ついくつもの江戸切子が並ぶショーウインドウに変貌をとげることでしょう。
その頃にはウェブだけでなく、広告に有効活用されているインスタグラムやツイッターなどを行使し、情報を発信してこの業界を盛り上げているかもしれません。
着こなしも作業着も、工房に乗り付けている自転車もさりげなくおしゃれで好ましいブランドであることも、三田村さんのセンスが表れているな、と感心させられました。

工房情報
haku硝子