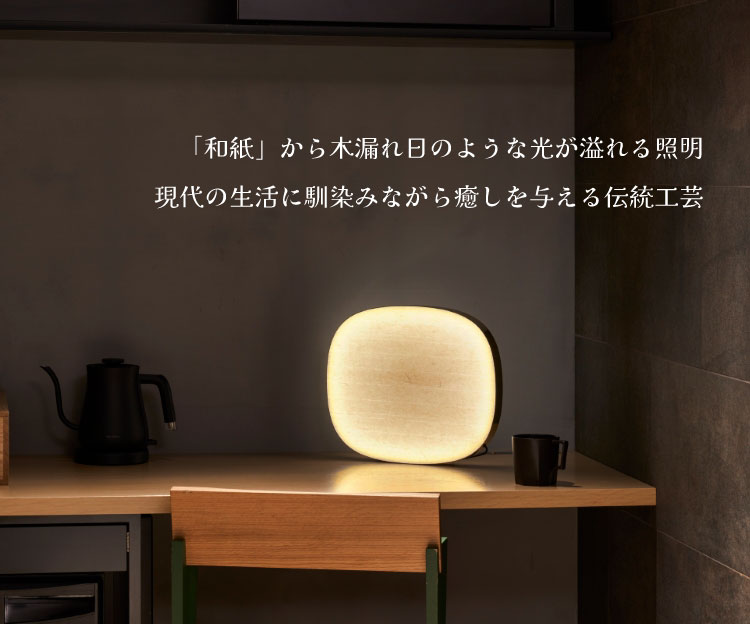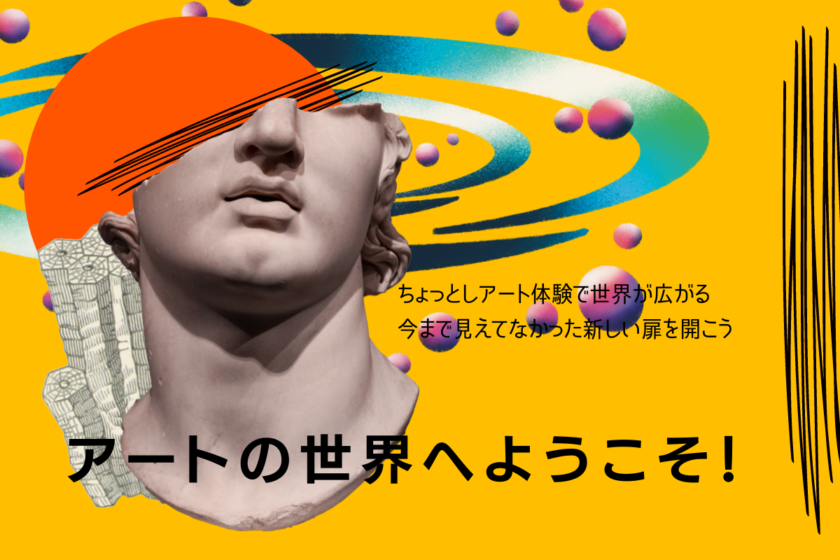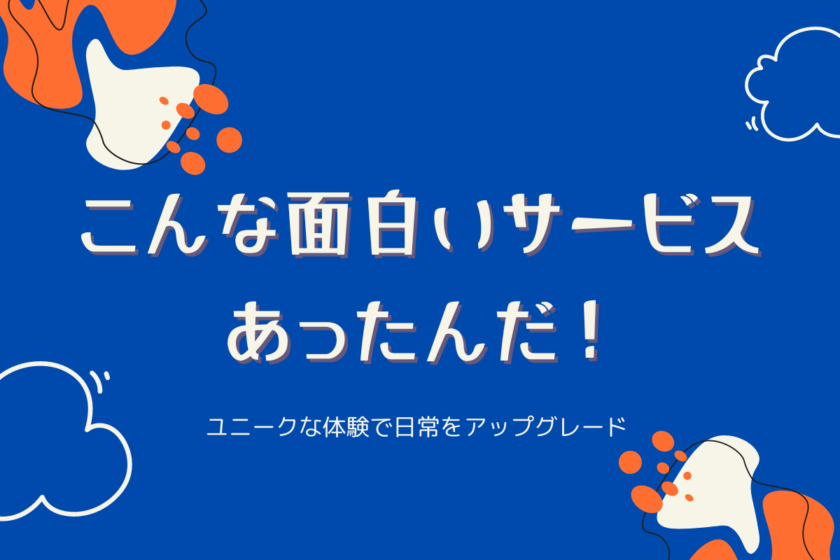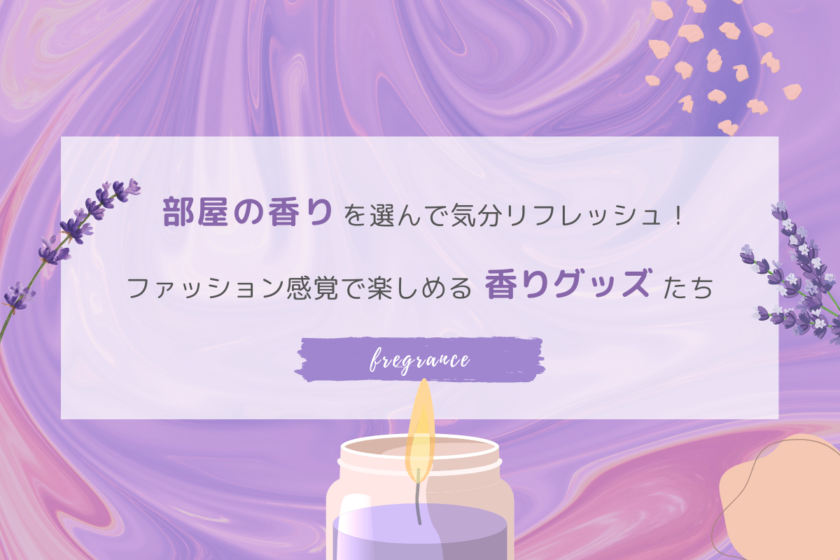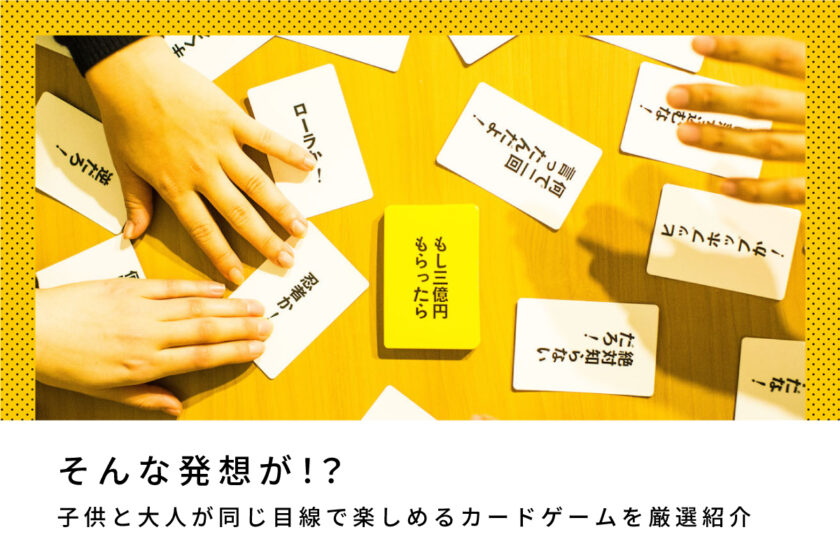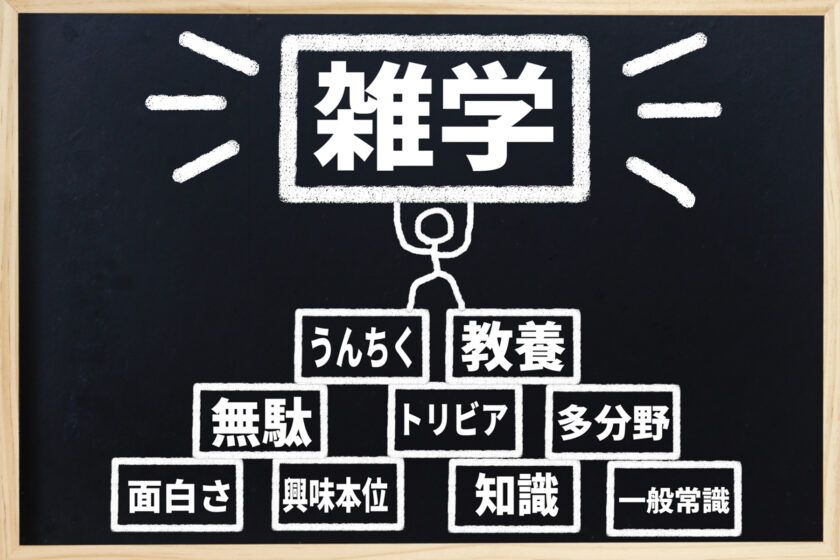今回紹介するのは、日本の「和紙(washi)」ではなく、カンボジアの「Ashi(亜紙)」です。「Ashi」を初めて聞く人も多いのではないでしょうか?
というのも「Ashi」は「和紙」のような長い伝統を持ったモノづくりではありません。まだ生まれたばかりの新しいモノづくり。その「Ashi」とはどんな商品で、どのようにして生まれたのかを詳しくお伝えしていきます。
世界初の水に濡れても破けないバナナペーパー「Ashi」

「Ashi」とは、カンボジア産の耐水性・耐久性に優れたバナナペーパーのこと。と、聞いても「ん?そもそもバナナペーパーってなに??」という人も多いですよね。
バナナペーパーとはバナナの茎からできたオーガニックペーパーです。バナナの茎を削ぎ、蒸し、糊付けして作られます。

そのバナナペーパーにさらに加工を施し、低融点ポリエステルを配合したのが「Ashi」です。
柔らかい紙の質感は残しつつ耐水性があって破れにくいのが特長。優しい手触りで和紙のような風合いを楽しめます。

その耐久性から、ポーチやバッグ、PCケースなどさまざまなアイテムを展開。デザインも豊富で色とりどりの商品が揃っています。
Ashiの由来は?

ちなみに「Ashi」という名には、こんな想いが込められています。
デジタル化が進むこの時代に 、 手作りでしか作れない バナナペーパー の温かみとしなやかさを備えた手漉きの 「紙」 が時代錯誤の波をかき分け 、 アジアのカンボジアから世界へ広がりますようにと思いを込めて 「Ashi(亜紙)」 と名づけました。
一般社団法人Kumae公式HPより引用
カンボジアの村が抱える問題

「Ashi」が作られているのは、カンボジア王国シェムリアップの中心地から少し外れたアンルンピー村。村の人たちが、ひとつひとつ時間をかけて丁寧に手作りしています。
そのアンルンピー村を知る上で避けては通れないのが雇用問題です。村に住む多くの大人・子どもが、村に隣接する大きなゴミ山で働いています。ゴミ山の中から、リサイクルできるペットボトルや缶などを拾い、業者に売ったお金で生計をたてているのです。

ゴミ山で働くうえで最も深刻な問題となっているのは、健康への被害。ゴミ山には「工場の有害廃棄物」や「病院の薬品・医療器具」なども含まれています。しかし、健康被害の危険性があるのはわかっていても働き続けなくてはいけません。それは、村に仕事が少ないため。

雨季・乾季があるカンボジアでは、農業や大工などは季節によって収入を得られる時期が限られてしまいます。その点、ゴミ山の仕事は季節を問わず収入を得ることが可能です。ゴミ山の仕事が村の人たちの生活を支えているという現実があります。
ゴミ山で働く村の人たちの仕事を生みだす「Ashi」

「Ashi」を販売しているのは、一般社団法人Kumae。ゴミ山で働く人たちのため、雇用事業や教育事業を展開しています。代表を務めるのは、山勢拓弥さん。当時20歳だった山勢さんが2013年に設立しました。
Kumaeの活動目的は「選択肢を広げること」

Kumaeの活動目的は「選択肢を広げること」。その活動目的を伝える上でHP内ではこんなエピソードが紹介されています。
ゴミ山で働く子どもたちに「将来つきたい職業」についてアンケートを行ったところ、約90%以上の子どもが「わからない、知らない」と答えたのだそうです。さらに、他の10%の子どもたちが知っていた職業もたったの4つ。「先生」「医者」「農業」「ゴミ山で働く」の4択でした。
その選択肢を広げるべく、山勢さんはKumaeを立ち上げたのです。
モノづくりによる雇用事業

職業の選択肢が少ないことは、ただ物資やお金を寄付するだけでは解決しません。自分たちで生み出す力やアイディアが必要です。
そこで、山勢さんが考えたのが、カンボジア初のバナナペーパー作りへの挑戦でした。ゴミ山で活動していた山勢さんが探していたのは「ゴミを出さないモノづくり」。捨てるはずのバナナの茎を使用したバナナペーパーは、まさにピッタリでした。
最初はポストカードから始まり、今ではKumaeオリジナルの「Ashi」に進化。「Ashi」には、ゴミ山で働く人たちの可能性を広げる希望が詰まっているのです。
カンボジアを代表する「モノづくり」へ

「Ashi」は始まったばかりのまだまだ発展途上のモノづくり。いつか日本の和紙のように、カンボジアを代表するモノづくりになっているかもしれません。「Ashi」がカンボジアの文化として根付いた時にはきっと、ゴミ山で働く人はいなくなっているのではないでしょうか。
商品情報
商品名 Ashi
販売元 kumae
商品販売ページ https://kumae.handcrafted.jp/2